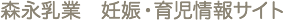Q&A
Q&A検索結果一覧
表示条件:月齢[] カテゴリー[全カテゴリー]
382件のQ&Aが見つかりました。
[森永商品:E赤ちゃん]
「チルミル」への切り替え方法は?
[森永商品:チルミル]
1歳からは「チルミル」?
1歳以降にミルクを使う場合は、「チルミル」と「はぐくみ」はどちらがよいでしょうか?(11ヵ月)


[森永商品:チルミル]
3歳以降も飲ませてもいい?
子どもが「チルミル」を好きで、3歳を過ぎた今も朝食とおやつの時に200mlずつ飲んでいます。食事はよく食べていますが、このまま飲ませ続けてよいですか?(3歳5ヵ月)
「チルミル」は幼児期のお子さまの成長に必要な栄養をバランスよく補うことができるフォローアップミルクです。牛乳にはほとんど含まれない鉄分やビタミンC、DHAなどを強化し、
母乳(特に初乳)に多く含まれ乳幼児の健康と発育に重要なたんぱく質であるといわれているラクトフェリンも入っています。砂糖不使用で甘すぎずあきのこない味ですので、
3歳以降も牛乳の代わりにお飲みいただけます。
関連商品


[森永商品:チルミル]
「チルミル」を家族の料理に使っていい?
「チルミル」を家族の料理に牛乳のかわりに利用してもいいですか?(2歳2ヵ月)
「チルミル」はクリームシチューやグラタンなど、牛乳のかわりに料理にもお使いいただけます。
「チルミル」は牛乳に比べて消化がよく、ビタミンやミネラルなど栄養バランスがよいミルクですので、ご家族皆様でご利用下さい。
関連商品


[森永商品:チルミル]
牛乳と「チルミル」の違いは?
子どもがもうすぐ1歳で卒乳しようと思っています。1歳を過ぎたら牛乳でもいいと聞きましたが、牛乳と「チルミル」の違いは何でしょうか?(11ヵ月)
この時期はよく食べるお子さまでも離乳食だけでは十分な栄養が摂りにくい時期で、特に鉄分の不足が心配されます。「チルミル」には、牛乳にほとんど含まれていない鉄分やビタミンC、DHAが多く含まれ、
離乳食だけでは摂りにくいカルシウムなどお子さまに適した栄養をバランスよく補うことが出来ます。また、「チルミル」は甘すぎずさっぱりとした味で母乳からの切り替えもスムーズです。
ぜひ、「チルミル」をお試しください。
関連商品


[森永商品:チルミル]
「チルミル」を離乳食に使えますか?
離乳食のシチューや味噌汁に「チルミル」を使いたいのですが、粉のまま入れてもいいですか?(11ヵ月)
「チルミル」は粉のままでも、一度溶かしていただいても離乳食の材料としてお使いいただけます。シチューやパンケーキなどメニューの内容により、量を加減しながらお使いください。
「チルミル」を使ったおすすめメニューが載っていますので、参考になさってください
関連ページ
関連商品


[森永商品:チルミル]
「チルミル」をコップで飲むときの作り方
「チルミル」をコップで与えてみようと思います。一度哺乳瓶で作ってからコップに移すほうがいいですか?(1歳)
「チルミル」は水で溶かすこともできますので、使いやすいと好評のフォローアップミルクです。「チルミル」は、調乳表にそって作ることをおすすめします。
「チルミル」を哺乳瓶で作ってからコップに移していただけますが、、目盛りのついているトレーニングカップなどをご使用いただくのもよいと思います。
関連商品


[森永商品:チルミル]
「チルミル」は1歳からしか使えない?
「チルミル」1歳以降しか使えないのですか?
1歳までのお子さまには「はぐくみ」・「E赤ちゃん」をお勧めします。9ヵ月以降で離乳食が3回食になっているようでしたら、「チルミル」をお試しください。
関連商品


[森永商品:チルミル]
母乳を飲んでいる赤ちゃんに「チルミル」を飲ませるとき
子どもに母乳を与えていますが、離乳食を少ししか食べないので、栄養が不足しているのではと心配です。試しに「チルミル」を与えてみたいのですが、飲ませ方のポイントなどありますか。(1歳)
どのミルクでも、今まで母乳しか飲んでいない赤ちゃんでは、はじめは哺乳瓶の乳首を嫌がったり、ミルクになじめない場合もあります。
はじめからトレーニングカップやストローをためしてみたり、母乳のにおいのしないご家族の方がミルクを飲ませてみるなど工夫してみましょう。卒乳することでミルクを飲むようになることもあるようです。
また「チルミル」は水でも溶けやすいミルクですので、いつもの離乳食メニュー(スープやおかゆなど)にプラスして「チルミル」をお使いいただくこともできます。
関連商品


[妊娠]
マッサージを受けてもいい?
腰痛があり、マッサージを受けたいのですが、おなかの赤ちゃんに影響はありませんか?(妊娠30週)
妊娠後期になると、多くの妊婦さんが腰痛に悩まされます。体重の増加や、おなかが大きくなることによる姿勢の変化で、腰にかかる負担も増えてきます。また、妊娠中に分泌されるホルモンの影響で骨盤のじん帯がゆるくなり、関節が不安定になってしまうことも腰痛の原因のひとつと考えられています。
腰痛対策には、日常生活で同じ姿勢を長時間続けないこととともに、軽い運動やストレッチが効果的です。マッサージも筋肉の緊張をゆるめ、リラックス効果があるので、血行もよくなり、痛みも和らぐようです。
ただ、腰痛は、生理的なものだけでなく、他の原因も考えられます。おなかの赤ちゃんや母体の状態によってもマッサージは控えたほうがいい場合もあります。必ず事前に主治医に相談してからマッサージを受けましょう。
マッサージの予約時には、妊婦さんにも対応できるか確認して、週数なども伝えておきましょう。当日の事前カウンセリングでも、うつぶせの姿勢は避けてもらう、子宮収縮を促すようなアロマオイルは使用しないなどを伝えてから受けるようにしましょう。
マッサージに行かなくても、ご家族の方に腰や背中を手のひらで押したり、さすったりしてもらう家庭でのマッサージもおすすめです。ストレス解消効果とともにおなかの赤ちゃんを含めたコミュニケーションもとれるので、一挙両得ですね。